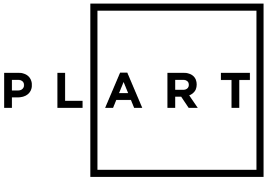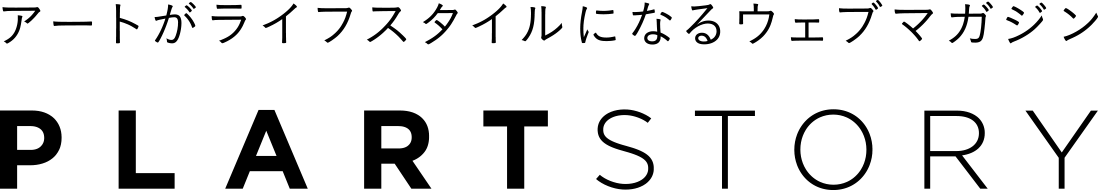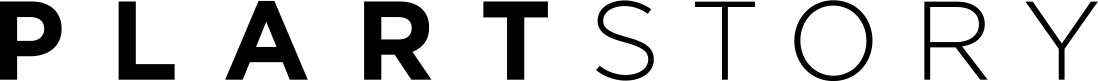【連載】アートがビジネスにくれるもの vol.2 「言葉だけでは、越えられないような壁を越えてしまえる力」groovisions代表 伊藤弘


6月15日号
連載「アートがビジネスにくれるもの」とは?
昔から、あこがれのビジネスマンには、アート好きな人が多かった。
その共通点はなんだろう?
それは、「人と違う視点を持っていること」ではなかろうか。
ゼロから生まれてくるアートが好きで、そして、自分も新しい価値を創る。
未開拓のシーンに挑戦するビジネスマンに憧れを持ち、少しでも近づきたくて、僕らは働く。
その人にはなれないけど、アートを通して同じ視点を取り入れる事は出来るかも?
アートには「新しい価値を生み出すヒント」がきっと、あるから。
デザイン集団「groovisions」(グルーヴィジョンズ)
これまで手がけた仕事にはピチカート・ファイヴなどミュージシャンのステージヴィジュアル、あらゆるグラフィック、ムービーやプロダクト、展示のディクレションまで。
その他にも、RIP SLYMEのアートディレクションも手がけ、アート関連では村上隆さんの展示ディレクション・カタログ集制作している。
多くの人から注目を集めた、 顔のパーツは同じだが髪型・服装・性別を変幻自在にできるキャラクター「Chappie(チャッピー)」もgroovisionsの作品だ。(表紙・左)
近年では自分のチャッピーを作れるアプリを発表し、SNSのアイコンをチャッピーにしていた人をよく見かけた。彼らの生み出す作品のいずれかを必ず「知ってる・見たことある」はず。
それほど、世の中へのアプローチが広いデザインを手がけ、持ち味の色鮮やかで、どこか遊び心のある世界観で注目を集め続けている。
オフィスには、等身大のChappieや、会社の名前入りのだるま、色とりどりの自転車が。そこに統一性はなくとも、どこかワクワクするオシャレなアイテムが所狭しと並んでいた。
今回、groovisionsを率いる代表 伊藤弘さん(以下 伊藤さん)の仕事観や自身のアートとの向き合い方についてうかがった。
アンディ・ウォーホルやナム・ジュン・パイク。当時を代表するアートの大スターたちに夢中になった学生時代

「僕はとにかく映像と映画が好きで、最初は映画監督になりたかったんですよ」
アンディ・ウォーホルやナム・ジュン・パイク(※)、横尾忠則など、70年代を代表する個性的で、刺激的なアーティストたち。その圧倒的な存在が伊藤さんを、アート、そして映像の世界へと誘い込んだ。
映画館へ通いつめる日々。映像に対するあこがれが次第に形を変え現実になったのは、伊藤さんが高校生のころだ。映像やアートを自分の手で表現する生き方へと、舵をゆるやかに切りはじめた。
※ナム・ジュン・パイク・・・ビデオアートの開拓者。韓国系アメリカ人の現代美術家。

「当時は、まだPCが全然非力だったので、ビデオ機器が最先端だったんです。ふとしたころから、そういうものを自分で組み立ててビデオアートを作りはじめました」
当時から手そのものを動かすより、機材を介してのアウトプットが好きだったと語る伊藤さん。
「デザインには、個人の個性も重要ですが、エンジニアリング的な側面があると思っているんです。それは、数値的な構造を基準につくるような感覚です。僕はそのエンジニアリングの部分が好きなんです。例えば、コンピューターの中で設計していれば、その後のアウトプットは様々なメディアを選ぶことができる」
その姿勢は、今のgroovisionsが作り出すものにも通じている。
個人「伊藤弘」から組織「groovisions」へ。フォーマットを作ること。

「個人の名前で、モノをつくる」
デザイナーであれ、作家であれ、個人の名前で勝負することは、同時にさまざまな責任を背負う覚悟をすることと同じだ。
伊藤さんは、それを自身が求めている時は心地よく感じることができるが、求めなくなった時には自分の自由をうばい、窮屈に感じてしまうことさえあると話す。
個人で活動していく過程で感じたそんな窮屈さを、ラップのようにくるりと包んでくれたのが、伊藤さんを筆頭に5人のチームから形成されるデザイン集団「groovisions」の存在だった。
「そもそも、ひとりで作品を生み出すよりも、groovisionsの組織の中のひとりとして一定の匿名性をもって活動する方が、より自由にモノが作れることに気づいたんです。自分だけの個性を反映した今までにないものを生み出さなきゃいけない!という無言のプレッシャーから解放されたんだと思います」

個人への重圧や、オリジナルを作るべきという神話から解放された伊藤さんが、組織groovisionsを通じて展開しはじめたのは、オリジナルの対極とも言える、デザインにおける工業製品の設計図の様なフォーマットを使った、あたらしい仕組みづくりだった。
その中のひとつが、代表作のChappie(チャッピー)だ。
渋谷ムーブメントの、ど真ん中で生まれた絶対的シンボル

1994年の渋谷。
街中のいたるところに音楽とファッションが溢れ、若者が熱狂する時代にgroovisionsのシンボルとも言えるグラッフィックアイコンのChappie(チャッピー)は生まれた。
「当時は音楽系の仕事が多く、渋谷系のムーブメントにどっぷり浸かっていたんです。とにかく音楽もファッションも、本当に面白かった。若い女の子が昔の高いレコードを、聴くためではなく、ファッションアイテムとしてホイッと買ったりする。そういう、何か時代を反映させられるようなものを作りたくて誕生したのがChappie(チャッピー)でした。ひとつのアイコンがあることで、自分たちのアウトプットできるチャンネルができるような気がしました」
groovisionsのアイディアをチャッピーを介してアウトプットすることで、豊かに表現することが可能になった。
人々にとって高嶺の花のモデルの様な存在よりも、リアリティのある等身大が好まれるようになった90年代。一般の人の体型に近く、親近感を抱くChappie(チャッピー)の存在は、まさに伊藤さんの時代をキャッチアップする力が生み出したシンボルだった。
Chappieに現れているgroovisionsの作品の特徴である、フォーマット化
機能性や合理性、規則性。あえてフォーマット化されたルールを作ることでgroovisionsの作品は息を吹き込まれる。
ところが、フォーマット化といってもgroovisionsの生み出すものはどれも、表情豊かな作品ばかり。どの作品を見ていても、とても一定のフォーマットがあるようには思えない。
「もちろん、固定化されすぎては面白くない。そのフォーマットの中にどんな要素を入れるのか。それはその時代、時代で変えていかなければいけないし、フォーマットそのものも変化していく必要はあると思います」
規則性を無視して中途半端に作ってしまえば、もちろんバランスも乱れてしまい、デザインとしてもきっとカッコ悪い。
groovisionsの作品がいつも新しく見えるのは、そのフォーマットを時代に合わせて「崩す」姿勢を徹底しているからなのだろう。
時代をキャッチアップしながら進むgroovisionsの力は、世間の「こうでなければいけない」というブレーキよりも、「好き」や「面白い」を素直に、臆することなく、追求して突き進んでいく原動力の方が、伊藤さん自身にあるからかもしれない。
アートには言葉だけでは、越えられないような壁を簡単に越えてしまえる力がある。
groovisionsの作品にはアートのエッセンスも活きていると話す。
「groovisionsとして仕事をする時に理屈を積み上げて積み上げて・・・最後に崩す!みたいな場面もよくあります。そんなところでアートの要素は必要不可欠かもしれません」
groovisionsのフォーマット化された連続性に、心地よい非連続を与えてくれるのが、アートの存在だ。
「0を1にする、言葉で越えられない壁を、越えてくれるアートが持つ力を上手く活かす。そのためにはまず「知る」必要がある」と伊藤さんは言う。
「日本人の良さはちゃんと雰囲気で消化できることです。でもアートも含めて雰囲気だけでは限界のある領域も思います。もう少しコンセプトとか、なぜそれがそうなってるのかをまずは、もっと気軽に勉強できる機会が日本に増えると良いなと感じています」
「なんとなくかっこいい」「なんとなく良い」ではなく、その作品のコンテクストを掴むことで、アートをより面白がれる可能性が広がる。

「アートを観てる量は多いのに、自分ほど買わない人は珍しい」と笑った。
「だけど、自分の好みや条件と向き合いながら『買う』を繰り返す行為は、漠然とアートを見ているよりも理解力が骨身になる感じが全然違ってくると思います。勉強することと、気に入ったものがあれば買ってみることは、アートを楽しむ上で結構影響することかもしれない」
連続性に、心地よい非連続のスパイスを与えてくれるアートの存在。
それが、groovisionsとアートの「切っても切り離せない関係」だ。
この先も、言葉やデザインだけでは越えられない壁に出会った時、アートの要素をうまく取り入れて楽しみながらその壁をふわりと越えていくのだろう。
kakite :古性 のち /photo by BrightLogg,Inc./EDIT by PLART & BrightLogg,Inc.

伊藤 弘/HIROSHI ITOU
アートディレクター。デザイン・スタジオ『groovisions』代表。1993年、京都で『groovisions』設立。グラフィックやモーショングラフィックを中心に、音楽、出版、プロダクト、インテリア、ファッション、ウェブなど多様な領域で活動する。 1993年京都で活動開始。PIZZICATO FIVEのステージビジュアルなどにより注目を集める。 1997年東京に拠点を移動。以降の主な活動として、リップスライムやFPMなどのミュージシャンのCDパッケージやPVのアートディレクション、100%ChocolateCafe.をはじめとする様々なブランドのVI・CI、『Metro min』誌などのアートディレクションやideainkシリーズなどのエディトリアルデザイン、『ノースフェイス展』など展覧会でのアートディレクション、MUJI TO GOキャンペーンのアートディレクション&デザイン、NHKスペシャル シリーズジャパンブランドや日テレ NEWS ZEROでのモーショングラフィック制作などがあげられる。