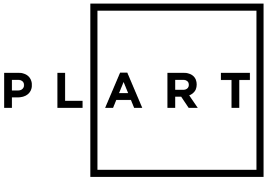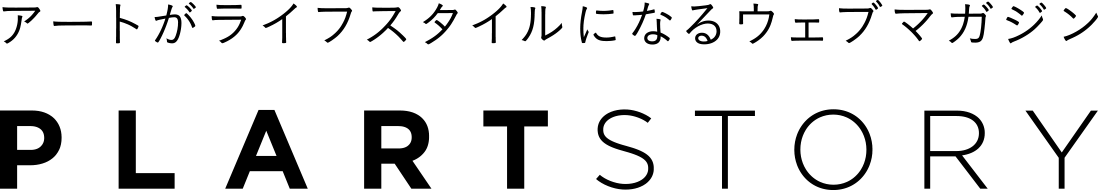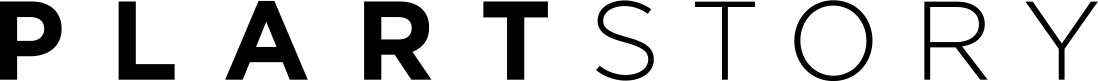【連載】アートとビジネス vol.8 「アートとは情熱を燃やして生きていくこと」 JTQ株式会社代表 谷川じゅんじ


3月15日号
JTQ株式会社代表の谷川じゅんじさん。その肩書きはスペースコンポーザーだ。
少し耳慣れない肩書きも、GINZA SIXのコンセプティングや、銀座蔦屋書店のアトリウムでのオープニングエキシビジョンを手がけた、と言ったらイメージが湧くだろうか。またアート好きな人にとっては茨城県北芸術祭「KENPOKU」のディレクターと伝えたら、ピンとくるかもしれない。
その他にも官公庁が主催する地域の魅力を発信する商業施設のアドバイザーとして参画、政府と一緒に日本の文化をどう活性化させていくかということを考えるほか、外務省JAPAN HOUSEロサンゼルスのエグゼクティブアドバイザーも務めている。
一方で全国のLEXUS店舗リニューアルのマスターデザイン、日比谷にオープンする東京ミッドタウン日比谷のレクサスの新店舗「LEXUS MEETS …HIBIYA」をプロデュース、ヨウジヤマモトのタッチポイントディレクションを手がけているなど、様々な枠組みで空間構成に関わる仕事をしているのだ。

GINZA SIX オープニングセレモニー/Photo: YAMAGUCHI KENICHI JAMANDFIX

銀座 蔦屋書店 EVENT SPACE Opening Program「Sensible Garden 感覚の庭」/Photo: Kozo Takayama
Yohji Yamamoto×Mika Ninagawa [BLACK LIGHTS], 2017(YOHJI YAMAMOTO AOYAMA)/Photo: Kozo Takayama
LEXUS西宮 / Masato Kawano (Nacása & Partners Inc.)
直近のプロジェクトは「Media Ambition Tokyo」。
2018年2月9日から2月25日、六本木を中心に都内各所を舞台に開催されたテクノロジーカルチャーの祭典だ。
国内外の様々な分野のイノベーターや企業、イベントが参画し、都市のあちこちで、テクノロジーの可能性を提示するような表現や体験が展開された。

多岐に渡るダイナミックなプロジェクトを手掛け、最先端の技術に人の創造が生み出すMedia Ambition Tokyoの指揮を執る谷川さんは「現在、価値観が大きく変わっていってます」と話す。谷川さんのクリエイティブの背景には何があるのだろう。
谷川さんがみつめる今という時代、日本のこれから、そして谷川さんにとってのアートとは。
記憶に残る空間のつくりかた
訪れたのは中目黒。間もなく満開の花を咲かせようとつぼみをふくらませる川沿いの桜並木を横目に、JTQのオフィスへと向かう。ビルの一角にあるオフィスの扉を開けると、その先には多様な色、形、素材のイス、机、ライトやオブジェの並ぶ空間があった。それぞれはバラバラで、どこの国からやってきたのだろうと思うぐらい個性的なのだが、明るく調和して美しく見える。




「どうぞ」と差し出されたミネラルウォーターのボトルは白と黒のボーダー柄。よく見るとJTQのロゴが入っていて、思わず「わぁ!」と声をあげてしまう。仕切りのない、オープンなミーティングルームに通されると、谷川さんの愛犬・ムツとランがこちらに顔を出してくれた。お話を聞かせていただく前から、わくわくが高まる。


愛犬・ムツくん
谷川さんの肩書きは「スペースコンポーザー」。
“空間をメディアにしたメッセージの伝達”をテーマに、様々なイベント、エキシビション、インスタレーション、商空間開発などを手がけている。
「コンセプトのデザインもするし、空間そのもののデザインもします。コンセプトをつくって、空間ができあがると、次はそこに体験が生まれる。コンセプトと空間と体験を結びつけることによって、ひとつのブランドを実感する現象になっていきます。
大きなものをつくれば人が来ていた時代もあるんですけど、今は大きなものをつくって人をたくさん呼ぶということよりも、小さくつくっても来ている人の質を問う時代になってきました。そのほうが結果的には広がっていくし、深度も変わってくる。量より質の時代になってるんじゃないでしょうか」
谷川さんが扱うのは空間。でもそれは例えば床や壁、天井だけの話ではない。
「空間というのを僕らは体験と考えています。空間に訪れる人々の気持ちには“期待”・“印象”・“記憶”があり、それに向き合います。期待を植え付けて空間に足を運んでもらい、印象があり、体験は記憶になってとどまる。記憶はワインでいうとテロワール、つまり土壌です。記憶の畑が肥えていると、種を投げたらすぐ芽がでます。だから、いかに記憶を豊かにしていくかが次のアクションにつながる。記憶をつくることが大切で、だけど難しいですね」

例えば私たちが期待を上回る美味しいごはんやさんに出会ったら、良い印象を受け、次は誰かを連れて来ようと、店の名前をメモしたり写真を撮ったりして記憶していく。そうして体験は記憶となっていくのだ。
「人生は記憶でできています。しかもその記憶って、コンテンツではなくてコンテクストなんですよ。
例えばさっきムツとランに会ったけど、“犬”はコンテンツで、“JTQにいる放し飼いの犬”がコンテクスト。人が反応しているのはコンテクストの方でしょう。今の時代はコンテンツよりコンテクストの方が重要だと考えているんです。物質的なものを物質から離脱させて、固有の価値に進化させていくのは、物語が全てだから」
扉を開けると色とりどり家具が並んでいて、ロゴ入りのミネラルウォーターのボトルを受け取る。そうしたJTQのオフィスに一歩足を踏み入れたときから起こった、アトラクションのような出来事を思い出し、記憶に残るのはコンテクストだ、という言葉に深く頷く。
資本中心の時代から文化中心の時代へ
谷川さんが「前提を共有するための地図」として見せてくれたのは、ひとつのシンプルな図表。縦に二列、キーワードが並び、左上には大きく20C、右上には21Cとある。

「変化をキャッチアップするために20世紀と21世紀を対比して整理しています。20世紀は資本が中心で、お金を稼ぐために課題を解決するというアプローチからいろんなものが生まれた。その結果世の中が便利になっていった。便利になることが豊かさの時代が確実にあったんです」
量産化するためにひな形をつくり、流行をつくることによって大量消費される時代が20世紀。その時代においては、画一性が本流だった。地方都市も次々と都市化し、「スモールトーキョー」がたくさんできていったのもその時代のことだ。そうした資本中心の20世紀に対して、21世紀は文化中心の時代になると谷川さんは話す。
「文化が中心になって、おのおのが課題解決ではなく、未来を見据えて考えるようになると、当然個性が出てくる。個性は言い換えるとブランド。コモディティに対して、ブランド化が進んでいく。そうしてみんながスタイルを確立すると、これからはそれぞれのライフスタイルを思考のベースに置いて考えるようになる。そうなると、全てはコンパクトにまとまっていくよね。これまでの都市という機能に対して、コミュニティや地域も顔が見えるようになって、交流によって暮らしが育まれるようになる。画一性に対して、多様性の時代になって、選択肢が増えていく」
例えば、と話題にあがったのは携帯のキャリア。確かに一昔前は、友人とメールをやりとりする際、キャリアが異なると絵文字が送れない、通話料が高いなどの不便さを感じることがあった。あの時代に比べると、今はキャリアの違いによるコミュニケーションの不自由さは解消されたようだ。デバイスも昔はアップルを使えるキャリアは限られていたけれど、今はどのキャリアでも使えるようになっている。今までの資本中心の20世紀の事情では受け入れられなかったことも、叶うようになってきているのが21世紀なのだ。
アートとは情熱を燃やして生きていくこと

そのような時代の変わり目において、「アートとビジネスはそれぞれの役割も目的も違うけれど、徐々にその距離が縮まっている」と谷川さんは感じている。例えばアート作品として提示されているものではない、商業的(ビジネス)なものの中にも、アートはあるのではないかと。
「ファッションデザイナーの山本耀司さんは“ファッションはアートじゃない。でもアートになる瞬間があるんだ”って話してくれました。僕はその感覚に共感を覚えます。普通のものの中にも、ハッとある瞬間心が奪われるものがあるというか。理屈じゃないところで、心を揺さぶられたり惹きつけられたりするものってありますよね。それはものかもしれないし、景色かもしれないし、空気かもしれない」
ビジネスを経済行為と置き換えたとき、これまでは、お金のために、豊かさのために働くという時代だったかもしれない。谷川さんはそこで立ち止まり、そもそもお金の本質とは何か、ということを言葉にする。
「お金の本質って“交換できる価値”ということだと思うんです。つまりある種のエネルギーですよね。“働く”って“人のために動く”と書きます。人は誰かのために何かをしたくて、喜ばれると報われる。だから、決してお金を得るためだけに働いてはいないと思うんです。働くことによって糧を得る、そうして自分が費やしたエネルギーが、次に自分が生きていくエネルギーにつながるような価値の交換がなされていく」
この糧や価値が、今お金と呼ばれているもの正体。だから、次に生きていくエネルギーにつながるよう、命を無駄にしないことが大事だと谷川さんは続ける。
「生まれてきたら全員死ぬわけですよ、いつか。だからどう生きるかということが大事になってくると思います。自分が命を燃やしながら、この時間を何に生かすか、そこがもっと問われる時代になっていくなかで、生活全部がアート化していくと思うんですね」

「生活の全部がアート化する」。その文脈(コンテクスト)でいう「アート」とはどういう意味だろう。もっと聞きたくなって、谷川さんに問いかけてみた。
「自分が暮らしている日々の生活のなかで、命を燃やすって話をしたけど、今日という日に何を産んだかということを問いながら日々過ごせていたら、時間が経ったとき大きな糧になると思うんですよね。
以前ある人に、“今日何が面白かった?”って毎日聞かれたことがあって。
“これが面白かった”と言ったら“それしかないんだ”と言われて、くやしいから翌日から面白いことをストックするようになったんです。そんな風に、“何が面白かった”という会話をするだけでも、1週間ぐらいすると暮らしが変わったりします。楽しいことを探すようになるんですね。
僕にとって、暮らしがアートに近づくってそんな感覚で。自分がより情熱を燃やして生きられるかどうかというようなことだと思ってます。アーティストってみんな情熱の人だと感じているので、“暮らしがアート化していく”というのは、“情熱を燃やして生きていく”ということです」
20世紀までの生き方には情熱を燃やしにくい状況(いわゆる既定路線にのった一丁あがり感)があったけれど、21世紀になって、暮らしの状況は変わった。多様な物事の価値観や生き方を肯定する先には、自分の生き方も変わる可能性があるかもしれない。だからこそ、ビジネスの領域にもアートな感覚が重要な要素になってくるのだ。
「生き方やお金の生み出し方も、創造性や情熱がビジネスのなかでも大事な要素になってくる。ビジネスがアート化していくというのは、例えば“儲けは少なくてもこれなら長く続けることができるよね”とか“自分らしさがある”、“情熱を傾けられる”とか。お金や合理性だけじゃない、新しい軸がこれから経済活動においても、いっぱい出てくると思うんです」
時代の流れを大きく捉え、例え話を交えながら、わかりやすく伝えてくれる谷川さん。その明快な語り口にすっかり惹き込まれる。そんな谷川さんの原点にはどんな体験があったのだろう。
ゼロから1の価値を生み出すことへの共感
「今の谷川じゅんじをつくった」そう言えるような出来事は、偶然にも、全て小学校3年生のときに起こっている。
そのひとつは、剣道。小学校3年生のときに始め、高校も大学も剣道推薦で進んだ武道家だった。その頃に学んだ日本らしい考え方や型の文化は、日本のアイデンティティを考える今の仕事に大きく影響している。
「これがふたつ目」と谷川さんが取り出して見せてくれたのは、絵日記。なんとこれがただの絵日記ではない。ページを開くと、折りたたまれた紙片が立ち上がる。「飛び出す絵本」形式の絵日記なのだ。絵の中には谷川少年も描かれている。


「この頃から空間的に物事を見ているんですよね。気に入っているのはこの熱が出た日の日記。寝ている自分の姿がポップアップになっていて。子どもの頃の僕の四畳半の部屋にござが敷いてあって、寝てるから視界にござしか入らない。だからござの模様がページいっぱいに描いてあります」
外から見えた自身の姿と、自分の視界の景色を融合させ、三次元的な空間の捉え方がひとつの絵の中に表現されている。
最後のひとつは、3年生から6年生まで出品し続けた「児童創意発明工夫展」。4年間ずっと金賞を取り続けた。
「3年生はつくったものを先生の配慮で展覧会に出してもらって、金賞をとってすごく褒めてもらったんですけど、4年生も出したらまた金賞になって。5年生から“金賞をとらないとかっこ悪いぞ”とちょっと意識して、親にインタビューして課題解決型の開発をやりました。
6年生になると、いろんな人から“金賞楽しみにしてるよ”と言われて、それがプレッシャーになって、期限の夏休みの終わりまで何も手につかなかったんです。最終的にプレッシャーでお腹を壊してトイレに駆け込んだときに、トイレットペーパーホルダーの紙交換がしづらくて、“あ、これだ!”と発明が生まれました(笑)」

金賞の発明品について説明してくれる谷川さん
剣道から学んだ日本の文化や意識、「飛び出す絵日記」をつくる空間的な感覚、そしてコンセプトを立ててデザインして発明品を提案していくこと。これらの3つが交わったところに、今の谷川さん像が見えてくるような気がする。
「ないものをつくるのが好きなんですよね。そういう意味ではアートも、ゼロから1の価値を生み出す人たちなので共感できます。僕はアーティストではないし、なろうと考えたこともないけれど、そういう人たちが集うことで、唯一無二の価値を生み出せることがあるなとずっと思っています。
アーティストやそれに準ずるような創造的行為をものすごいエネルギーでやっている人たちを、ビジネスに近いところでサポートする仕組みができれば、それが違う可能性を生み出すんじゃないかと思っていて。それの磨き上げた必殺技が僕にとって、Media Ambition Tokyoです」
海外の人が日本を訪れるチャンスをつくる
2018年2月9日から2月25日に開催されたMedia Ambition Tokyo。2013年に始まり、今回で6回目を迎えた。日本発のテクノロジーカルチャーを発信していく場として、世界を見据えて開催している。その背景には、国内だけではなく、海外からも注目されるような日本であることが大事だという考えがある。
「日本はこれから国民の数が減って、どんどん高齢化していきます。そのときに国力が弱くなるかもしれないけれど、どうやって世界と向き合ったらいいだろうと僕なりに考えてみると、尊敬される国になることが大事だと思うんです。日本は2000年を超える歴史がある、世界屈指の長老国です。だから体力は弱くても、精神的な柱としてみんなに頼りにしてもらえるような地球村の長老になれるような存在になれたら、高齢化しても、それはそれで幸せに生きていく方法が見つかる気がしているんです」
人が集い、興味を持ってもらうための仕組みづくりを長年仕事にしてきた谷川さん。海外の人に日本へ関心を向けてもらうためにも、コンセプト・空間デザイン・体験デザイン・ブランディング、その4つを同時に考えていくことが今後も大切だと話す。
「今は日本を訪れるのはアジアの人たちが多いですが、これがずっと続くかもわからない。旅行客の数が全てではないけれど、常に世界に興味を持ってもらう対象でいられるかどうかは、自分たちの努力次第だと思っていて。そういう意味でこれからも、海外の人が日本に来てくれる機会やチャンスをつくっていきたいです」
今まさに20世紀から21世紀へと価値観が大きく変わっていく時代。
谷川さんは自身のことをアーティストではないと言ったが、「日々自分のしていることに情熱を傾けられる人」がアーティストであれば、谷川さんはもちろん、私たちひとりひとりがアーティスト的な感性をもって生きる時代になっていくのだろう。
そうした大転換期にあって、谷川さんは世界の中での日本のポジションや自身についても客観的に観察し、ひとつひとつ言葉にしているように感じた。そう、小学校3年生のときに飛び出す絵日記をつくったような視点で。
「流されずに生きていきたいなと思いますよね。流されるとスピードは早いけど、どこに行くかわからないので。ちゃんと歩いていくのがいいんじゃないかな。自分の足で」

kakite : Naco Fukui/ photo by Yuba Hayashi(クレジットがあるものを除く)/Edit by Naomi Kakiuchi

谷川じゅんじ/Junji Tanigawa
JTQ代表/スペースコンポーザー
2002年、空間クリエイティブカンパニー・JTQを設立。 “空間をメディアにしたメッセージの伝達”をテーマに、さまざまなイベント、エキシビジョン、インスタレーション、商空間開 発を手掛ける。独自の空間開発メソッド「スペースコンポーズ」を提唱、環境と状況の組み合わせによるエクスペリエンスデザイ ンは多方面から注目を集めている。主なプロジェクトとしてパリルーブル宮装飾美術館 Kansei展、平城遷都1300年祭記念薬師寺ひかり絵巻、NIKE WHITE DUNK、YOHJI YAMAMOTO Exhibition、GINZA SIXグランドオープニングセレモニーなど。
2018年現在、外務省JAPAN HOUSEロサンゼルス エグゼクティブアドバイザー、MEDIA AMBITION TOKYOアーティスティックディレクター、東京ミッドタウン日比谷 LEXUS meets… hibiya 総合ディレクター等を務める。
取材フォトギャラリー