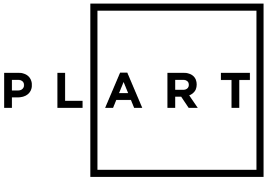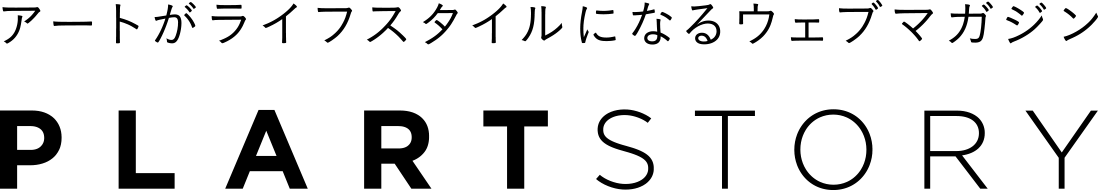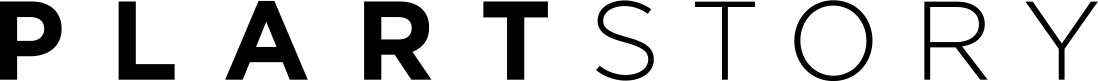【連載】アートとビジネス vol.9「アートとサイエンスのリバランス」コーン・フェリー・ヘイグループ株式会社 山口周


4月15日号
今、日本のビジネス界を席巻している1冊の本がある。そのタイトルは『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』。
この本には、「分析」「論理」「理性」に軸足をおいた「サイエンス重視の経営」の限界と、「直感」や「感性」など内在的な美意識(アート)を取り戻し、両者のバランスを調整することの大切さが、様々な実例を交えながら論考されている。
「これまでモヤモヤしていたことをよく言語化してくれた!」そんな共感の声を集め、ベストセラーとなっているこの本の著者は山口周(やまぐち・しゅう)さん(以下、山口さん)。組織開発と人材育成を専門とするコンサルティング会社、コーン・フェリー・ヘイグループ株式会社(以下、ヘイグループ)のシニア・クライアント・パートナーだ。
これまでにも組織論やキャリア論に関わる本を多数出版している山口さんだが、今回の本を執筆するときには、過去の本と意識的に変えた点があるそうだ。

世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?経営における「アート」と「サイエンス」(光文社新書)
「これまでは必ず根拠を示すという『サイエンス』の方法に忠実に書いてきました。ただこの本ではこれまでのやり方を外して、根拠はないけれど自分はこう思う、という直感や感性、つまり『アート』を大事にして書いている部分があるんです。そうして書いた本が世の中から共感の声を得られた、というのは発見でしたね。」
ひとつひとつ言葉を選び、おだやかな口調で語る山口さん。
大学では哲学、大学院では美術史専攻、そして現在はコンサルティング業界という異色の経歴を持つ。
「アート」と「サイエンス」。二つの要素をどちらも内包する山口さんは、どんな幼少期を過ごし、これまでどんな選択をして歩んで来たのだろう。これまでのキャリア、原点、そして日本におけるビジネスと美意識のこれからに迫った。
「アート」と「サイエンス」の点と点をつないで描いたキャリア
「よく人から美術史をやってなんでこんな仕事やっているんですか?と聞かれることがあります。海外では美術とビジネスの領域をキャリアとして行き来する人もいるんですが、日本ではあまり一般的ではないですね」
そう語るように、山口さんは大学院では美術史を専攻し、キュレーティングを学んでいた。
大学院卒業後、アートや表現に関わる仕事がしたいと考え、選んだ職場が株式会社電通(以下、電通)。企画・展示や表現に関わる仕事を志し入社したが、「向いていそうだから」と配属されたのは、まさかの営業。20代を営業一色で過ごした。
やがて担当していた外資系のシューズブランドで、これからのトレンドや販売促進について議論に加わる機会があり、会社の方向性についてアドバイスをすることを専門にする、コンサルティングファームという仕事があることを知る。
「面白そう」そんな直感で転職したのはボストン・コンサルティング・グループ(以下、BCG)。30代は事業戦略づくりや会社の売却などグッとビジネスよりの仕事をすることになる。
40代になりフィールドを変え、現在の職場、組織や人の領域を専門に扱うコンサルティング会社、ヘイグループへ加わった。
『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』に書かれている、経営が「サイエンス」に偏りすぎていることに課題意識を感じ始めたのは、ヘイグループへ入社してからだ。

「組織や人材のコンサルティングをやっているうちに、なんでこんなに組織に元気がないんだろう、生き生きと仕事している人があまりいないんだろう、と思うようになったんです」
日本では転職をしないでひとつの会社にいるという人も多いが、山口さんによると、会社や仕事に対する愛着は先進国の中でも断トツの最低水準なのだそう。日本のビジネスが強くならない、その根っこには、個人が会社や仕事に誇りを持てていない状態があるのではないか。
「まれに出会う生き生きと仕事をしている人に話を聞くと『世の中こうなったほうがいい』とか『こっちの方がかっこいい』とか、個人の感性で自分らしさをドライブしているんですよね。日本が元気になるにはこっちの方向なんじゃないかと感じたことで、アートや美意識と結びつきました」
クリエイティブとビジネスの領域で仕事をしていた20代から、ビジネス寄りの30代へ。40代になってから、ビジネスとアートが結びついたのは、山口さんにとって「これまでの点と点が線でつながった」そんな感覚があったという。
科学雑誌と美術全集、そしてピアノのある暮らし
話の道筋をロジカルに組み立てる一方、時には冗談を交えながら話し、茶目っ気たっぷりな人柄であることが伝わってくる山口さん。
いったいどんな幼少期が、山口さんのアートとサイエンスの感覚を育んだのだろう。
「環境に恵まれていましたね」

そう話す山口さんのお父様は銀行にお勤めで、お母様はピアノの先生だった。
「家には父親が購読している科学雑誌ニュートン、数学者のジョージ・ガモフの全集があって。とっても面白いなと思って読んでいました。小学生の頃から理論物理が好きで、そういう意味では小学校から中学校までは理数の興味が強かったかもしれないです。
一方で祖父母の山荘には、平凡社の世界美術全集がありました。夏休み家族で行ったときに開いてみるんですよね。そうするとゴヤの絵が飛び出してきたりして、なんじゃこりゃ!?という衝撃がありましたね」
特に忘れられない景色として山口さんが話してくださったのはお母様がピアノを弾く風景だった。
「小学校3年生ぐらいのときかな。秋の夕方なんですけど。家に帰ってくると、ショパンの幻想即興曲の間奏の部分を母が弾いていたんですね。練習に夢中になって、部屋の明かりもつけずにいて。夕日がバッと部屋の中に差し込んでいて。それは息が止まるような風景だったんです」
いつもの家の景色が、音楽や光によって全く違った美しいものに見える。それは日常を「異化」させ、新しい文脈を切り出してみせる、ひとつのアート体験として山口さんの心に刻まれている。
やがて音楽をつくることへ興味を示し、高校一年生から大学院を卒業するまで作曲の勉強をしていた。音を数字に置き換えて構造をつくる作曲の手法は、数学とも近いものだと感じていたそう。

山口さん自身も幼い頃からピアノを弾き始め、現在も弾き続けている。(写真:山口さん提供)
こうして音楽や理数への興味を山口さんの背景として伺っていると、大学で専攻した「哲学」というキーワードがポンと宙に浮いてみえる。なぜ哲学科へ?と質問すると、答えは意外にも「かっこいいと思ったから」。
「高校生のとき、みんなは楽しそうにしているんですけど、正直クラスメイトになじめないでいたんですね。そんなときにニーチェの『ツァラトゥストラかく語りき』を読んだんです。そしたらそこには自分が思っているようなことが書いてあるわけですよ。当時、書いてあることの全てを理解していたわけではないのですが、ところどころ共感できたり、かっこいいなと思う言葉があったりして。それで哲学科へ進みましたね」
山口さんの話を聞いていると、論理的に考えながらも、最後は「かっこいいから」「面白いから」そんなご自身の感性の部分が大きな決め手になっていることがわかる。
「アート」と「サイエンス」、両者は相反するものではなく、常に山口さんの中で両立し、調和するものだった。
これからの時代を生き抜くための創造性
著書には「『直感』と『感性』の時代」とある。山口さんがこれからの時代と創造性を考える上で外せないと話すのは、人工知能の存在。チェスや将棋などすでにコンピューターが人間を凌駕し世界一になっている。
しかし、例えば音楽をつくる、絵を描く、小説を書くといった、クリエイティビティの領域では人工知能では及ばない部分がある。
「人工知能に音楽をつくらせる研究は70年代から始まっているのですが、未だにその音楽は聴くに耐えうるものではありません。バッハの音楽を大量に覚えてバッハ風の曲をつくるということはなんとなくできるんですが、それって創造じゃないでしょう。創造ってその人固有のものを生み出す作業だから」
こうした個々によって質や個性の差がでる領域はコンピューターにはなかなかとって代わることが難しい領域なのだそう。だからこそ人間がアドバンテージを発揮できるのもその領域になってくる。
「『感性の時代』というのは、感性や創造性が大事だと見直されるというわけではなくて、人と人工知能の競争になったときに、競争戦略上やむをえず、追い込まれることで発生してくる事態だと思います。創造性を発揮してコンピューターを使う人と、能力がなかなか発揮されずにむしろコンピューターの部下になってしまう人。人はこれからその二つに分かれていくと思うんです」
そうした時代にあって、組織や個人が生き延びていくためにはやはり創造性を育むことが大事になる。そのためには、自分が何を大切にするか、内側にモノサシを持つことが必要だ。
「何かを判断するときのモノサシが徹底的に外在化している人がいますよね。例えば『どんな仕事をやりたいかはわからないけど、世の中の人気が高いから大きい企業を受けることにしました』という学生や、『マーケティング的に正しいからやります』という経営者がいるように。本来は自分がやりたいからそれを世の中に届けるためにどうしたらいいかが先行するものでしょう。

自分の人生って、本来はアート作品的な唯一無二のもので、どう生きたい人生を描いていくかということなんです。人から外在的にやることを決められていると、何をやりたいかがわからなくなってしまうんですよ」
そうした個人が変わるためには、世の中の価値観を揺るがすような大きな変化がパラダイム・シフトへつながるひとつの契機になる。
「世の中で過去2,30年調子が良いと信じられていたものが、完全に裏切られる形で変わっていくということがたくさん起こってくると、結局自分が何をやりたいんだろうということを考えていかないと生きていけないという状況になっていきます。
自分がこうしたい、これがクールだ、自分らしい、そういうことを感じ取るアンテナがピカピカしてくると個人が変わり、社会全体の状況が変わってくるんじゃないですかね」
周囲5メートルの人が自分らしい豊かな人生を送れるように
人工知能の登場やパラダイム・シフト。そうした社会の大きな変化についてお話を伺ったあとに、山口さん自身のこれからの指針について尋ねると、返ってきたのはとてもシンプルな答えだった。
「僕は自分自身や身の回りにいる人を幸せにしたいと思っているだけなんです。だから住みたいところに住むし、ものすごくストレスがかかるような仕事はしたくないし、自分が素敵だと思えるものに触れていたいです」
現在、葉山でご家族と暮らす山口さん。山口さん自身もピアノを弾いたり、音楽を聴いたり、絵を描いているという。子どもには同じようにすることを強要するのではなく、楽しんでいる様子を見せてあくまでも自然体でいるようだ。その眼差しはあたたかい。
「うちの子どもたちを見ていると、きれいなものをみつけてくるんですよね。コーラの瓶を目に当てて外を見るときれいだよ、とかね。

自然の中で暮らすお子さんとの日々は山口さんにとって心が揺さぶられること担っているようだ。(写真:山口さん提供)
現代アートって、人の感性を揺さぶるものであればなんでもアートになるということを許容しているでしょう。だから、このコーラ瓶で景色を眺めたらきれいに見えた、というのはひとつのアート体験だと思うんです」
現実をいつもと違った文脈の上に取り出してみる。その姿は、山口さん自身が、ショパンの幻想即興曲を弾くお母様のピアノの音と秋の夕暮れに美しさを感じた姿とも重なる。
アート体験とは、楽器を演奏する、絵画を描く、それだけではなく、これまでと異なる角度で物事を捉え、そこに自身の基準で美しさや面白さを見出すことなのかもしれない。
「僕は『素敵』や『ときめき』が重要なキーワードだと思っていて。そう感じる心を大事にしたいし、自分が素敵だと思ったり、ときめきを感じたりするものに携わって生きていくことが大切だと思っています。世の中のモノサシじゃなくてね。

ひとりひとりが周囲5メートルにいる人たちに対して、自分らしい豊かな人生を生きられるように心を砕くこと。それによって自分のモノサシを大切にすることができる環境をつくれたら、世の中はもう少し生きやすくなるのではないでしょうか」
自分の幸福とは何なのか、またその幸福は自分自身だけで成り立つものではなく自分と相手があって成り立つものではないのか。
〜君よ、大いなる星よ、いったい君の幸福もなにものであろうか、もし君に光り照らす相手がいなかったならば〜 ニーチェ『ツァラトゥストラかく語りき』序説
数字や論拠の重要さ。自分の内側に宿るときめきや美意識の必要性。
サイエンスとアート、どちらも内在する山口さんの土台は、自分の手が、目が、声が届く近しい人々の幸せである、という言葉はまるでニーチェの言葉にも重なるようで、山口さんご自身のモノサシで測った哲学のようにも聞こえた。
kakite : Naco Fukui / photo by Naoki Miyashita (提供画像除く) / Edit by Chihiro Unno

山口周/Shu Yamaguchi
1970年東京都生まれ。慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科美学美術史学専攻修士課程修了。電通、BCG等を経て現在、コーン・フェリー・ヘイグループのシニア・パートナー。(株)モバイルファクトリー社外取締役。一橋大学商学研究科非常勤講師。(株)ライプニッツ代表。