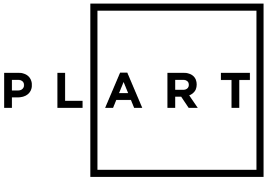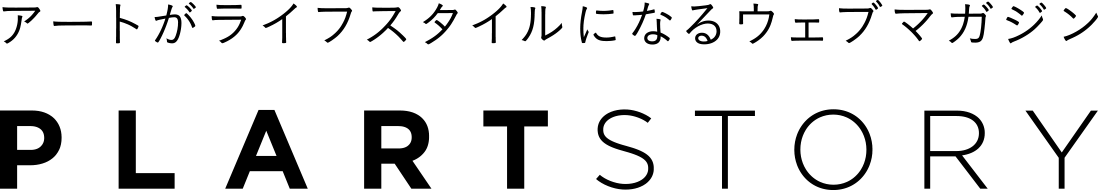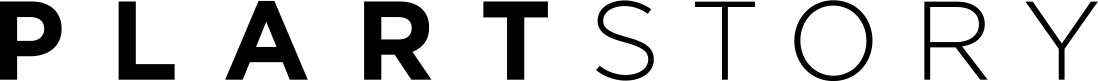身にまとうことが、本質を知るきっかけになる【アーティスト 高橋理子】


9月15日号
――魅力的になるためのマストアイテム!
――今年のモテ色はこれだ!
“流行に乗せる人と乗せられるひと”。
その関係性は、インターネットによって多様な姿の人々が見られるようになった今日でも変わらない。
本当の自分とはどんな人物なのか、自身が周囲に与える影響はどんなものなのか……。
いろいろな物事が右から左へ流れていくなか、そのようなことまで考えている人がどのくらいいるのだろうか。
「服を着るということは、外に纏いながら自分の内側に向き合うことだと思うんです」
円と直線の図柄が特徴的な着物やテキスタイルを中心に、様々な作品を生み出しているアーティストの高橋理子(たかはしひろこ)さんはこう語る。
高橋さんの活動理念は、「固定観念を覆す」。
それは、プロダクトレーベル「ヒロコレッジ」を立ち上げる時に形になって出てきた言葉だという。
生み出すのは、消しゴムがコツンと当たるような小さなきっかけ

“きりっとした人”。
それが、高橋さんの第一印象だ。自身の作品に身を包み立つ姿は、芯がすっと通っていて、静かだけれども華やかで素敵な空気感をまとっていると感じた。高橋さんが目指しているのは、単に“素敵”や“かわいい”“美しい”というような言葉で表現できる作品を作ることではない。
「『ヒロコレッジ』設立のときに、それまで考えてきたことを全部並べ出しました。そして、私にとって重要なことは、ものごとの本質に向き合うことだという結論に至ったのです」
そう言う高橋さんの笑顔には一切の淀みもない。
自由な家庭環境で育った高橋さんは、幼少期に父親が愛読していた自動車専門誌を読み、弟と自動車を描いて遊んでいた。そんな高橋さんにとって、赤いランドセルを背負うのが当然とされていた女の子という枠組は窮屈なものだった。表層的で本質的ではない、世の中の固定観念による生きづらさをなくすために、人々が考えるきっかけとなる作品を手がけているという。
「例えば、今買ったものが本当に自分の好きなものなのか、単に自分の好みを自分自身にしっかりと問いかけるだけでも、自分に意識を向けることにつながります。些細なことにも疑問を持ち、考えるということは、私たちが生きる全てのことにおいて必要なことなんです。
自分自身の本質に向き合い、自身を理解し行動することは、他人を理解することにもつながっていく。人々が互いに理解を深めることができれば、戦争も無くなるかもしれません。私の活動が人々に影響し、最終的には世界平和につながればと考えています」
お話を伺いながら思った。フェアトレード品やオーガニックな素材を使った“エシカルファッション”も、身の回りで起こっていることに気が付いた人が行動した結果だ。人が争う理由は様々だが、もしかしてその理由にお互いが向き合えば、世界平和は本当に実現するかもしれない。
しかし、考えることを強要すべきではない、と高橋さん。自分で気づき、能動的に考えたことこそが、それぞれの内で定着するからだ。
「私の作品では、消しゴムがコツンと軽く頭にあたるくらいの小さな違和感を感じる表現を目指しています。その小さなきっかけによって『あれ?何かおかしいな、何でだろう?』と、どんどん考えを巡らすようになると思うんです。
例えば、着物や浴衣をまとった際に、美しい姿勢について考える。そうすると、日常における姿勢や所作についても意識するようになり、新しい自分に気づくことができるかもしれません。着物を手掛けている理由の一つはそこにあります」
作品には考えるきっかけとなる様々な仕掛けが散りばめられている。そのうちの1つが、高橋さん自身の仁王立ちによるポートレートやマネキンだ。


「仁王立ちは、柔道をやっていた私にとっては自然なポーズですが、着物を着て仁王立ちしている女性はあまりいませんよね。『どうしてこの人は仁王立ちなんだろう?』って思ってもらうことをきっかけとして、ジェンダーや着物に関する思い込みなどにアプローチできればと考えています」
着飾らないことは、素の自分を見てもらうこと
服を身にまとうことで自分や世界の本質を発見できる。では、着飾ることについては?
「私自身は、着飾れば着飾るほど自分が無くなると感じています。特徴的なものを身につけると、誰かに似たり何かに見えたりして、自分のアイデンティが見えづらくなるからです。2016年の9月にデコ屋台を作ったんですけど――」
「デコ屋台」とは、日本仕事百貨の「しごとバー」という企画の中で、建築家の佐野文彦氏とともに、生み出した作品。デコトラから着想を得た「屋台」。しごとバーにおける、人々の交流のステージとして活用されている。
高橋さんはこのプロジェクトでコンセプト設計を担当。デコトラを調べるなかでわかったのは、臨海地域で漁業関連に従事するトラックが塩害で錆びたところを、柄の入ったステンレスの板などで覆ったのがデコトラの起源だということ。元々は傷んだ部分を隠していたのが、後々装飾に変化したのだ。
「トラックを金属板で修復するのと一緒で、“着飾る”という行為は、欠点を隠すことにつながる。そう捉えると“飾らない”ことは、素の自分をさらけ出すことになりますよね。
実は、私自身は人前に出るのが苦手で、本当は透明人間で生きていたいくらいなんです。笑 なので日常ではシンプルにものを身にまとうことであまり目立たないようにしています。でも、だからこそ本当の私を見てもらえるのではないかとも感じています」

人前でも着飾らず、自分自身を見せるのは、相当な勇気のいることだ。しかし、6歳の時にはファッションデザイナーになると決めて大学で染織を学び、夢に向って邁進し、何よりも「枠にはまりたくない」と強く思う高橋さんには、自然なことなのかもしれない。
洋服一筋だった学生時代を経て「着物」に向き合うことを決めた瞬間
「幼少期からずっとファッションデザイナーになりたくて服飾デザインを学べる高校に進学しました。ジャケットやワンピースをデザインして、パターンをひき、縫製まで学んでいるなかで、どうしても気に入る生地が見つからなくて。そうしていたら、『オリジナルの生地から服作りをしたければ染織を学んだら良いよ』と先生からアドバイスをいただきました。
大学では、課題で染めた布ををシャツなどの着用できる形に仕立てて提出していました。当時はファッションの専門学校の人たちとファッションショーを開いたり、インディーズブランドを立ち上げたりして、いつも頭の中は洋服のことで一杯でした」
高橋さんが、着物を活動の中心にすると決めたのは博士課程にいた頃だ。
「着物と出会ったのは大学からですが、当時は、着物を学べば他の国の人達とは違った感性を持ったファッションデザイナーになれるのではないかと軽い気持ちで着物に取組んでいました。しっかりと着物に向き合おうと思ったのは、2005年にフランス外務省から招聘され、パリで活動していた時です」
パリで開催した着物の展覧会で、「着物というすばらしい日本の文化に関わることができるなんて本当に素晴らしいこと。うらやましいわ」とフランス人のマダムに言われ、初めて自分自身の状況について俯瞰的にみることができました。

「それまで私の中で“着物”という存在は、あくまでもファッションの為のものでしたが、世界での着物の評価が、私が理解していた以上に高かったということを実感しました。ファッションの系譜においても、着物が強い影響を与えてきたことは事実ですが、それ以上に、衣服としての側面だけでなく、様々な要素が着物にはあるということに気付き、さらに深く向き合うことを決断しました」
高橋さんの現在の活動につながる覚悟が決まった瞬間だった。
内面をそっくり映すようにデザインされたスタジオ
高橋さんのスタジオは、墨田区にある。白が基調のすっきりとした空間で、設計は清澄白河や中目黒にある「ブルーボトルコーヒー」の店舗なども手がけた建築家 長坂常さんによる。
設計を始める前に言われた「高橋さんがどういう人生を歩んできたのかが重要」という長坂さんの言葉を受け、ふたりは幾度も対話を重ねた。
「会う度に長坂さんから沢山の質問を受けながら、私の幼少期からの話をしました。そして、表現方法に固執せず自由に活動していきたいというこれまでの私の考えと共に、明日まったく別のことをしたいと思った時にすぐに対応できるような、自由な心持ちで活動できる場にして欲しい、と伝えました」
対話を重ねた結果、全てのものが床に固定されていない、自由度の高い空間がうまれた。



「私の内面をそのまま反映した、私の奔放な性格を許容する柔軟性の高いスタジオになりました」と満足そうだ。
スタジオ内には、円と線の柄の作品たちが、引き立て合うように並べられている。
10年の活動で得た、新しい考え

高橋さんが「デザイナー」ではなく「アーティスト」と名乗っていることに疑問を持つ人もいるのではないだろうか。そこにも、高橋さんの思いが込められている。
「活動当初から、枠組みにとらわれたくなかった私は、本当は肩書をつけたくありませんでした。例えば建築やグラフィック、ファッション、テキスタイル、陶芸など、作るものの名称が肩書になっている場合が多いですよね。でも、私は自分の理念を表現する方法を限定したくなかったんです。既存のものによる制約を受けずに、表現者という意味で、“アーティスト”がすべてを内包できる自分が自由でいられる肩書きだと思っています」
高橋さんの会社は、昨年末に設立10周年を迎えた。着物への新しい思いが芽生えているそう。
「着るための着物の販売を本格的に始めることにしたんです。これまで着物は私にとってコンセプチュアルな表現媒体でしたが、10周年を機に気持ちを切り替え、新しいステージで着物に向き合うという決心をしました。これからも着物の可能性をさらに深く追求していきます」
枠にとらわれず明日は何をしているかわからない、という自由な姿勢に触れ、私もどんな遠くへでも飛んでいけるような気がした。
kakite : 松本麻美/photo by 花坊 /EDIT by PLART

高橋 理子/Hiroko Takahashi
円と直線のみで構成された図柄により、独自の活動を展開するアーティスト。
2008年、東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課程を修了し、博士号を取得。
固定観念をくつがえし、考えるきっかけを生み出すことをコンセプトとした作品を、国内外問わず発表している。
着物を表現媒体とした創作活動のほか、日本各地の伝統技術を持った工場や職人とのもの作りをおこなうなど、
様々な企業や産地とのコラボレーションも多く、活動は多岐にわたる。